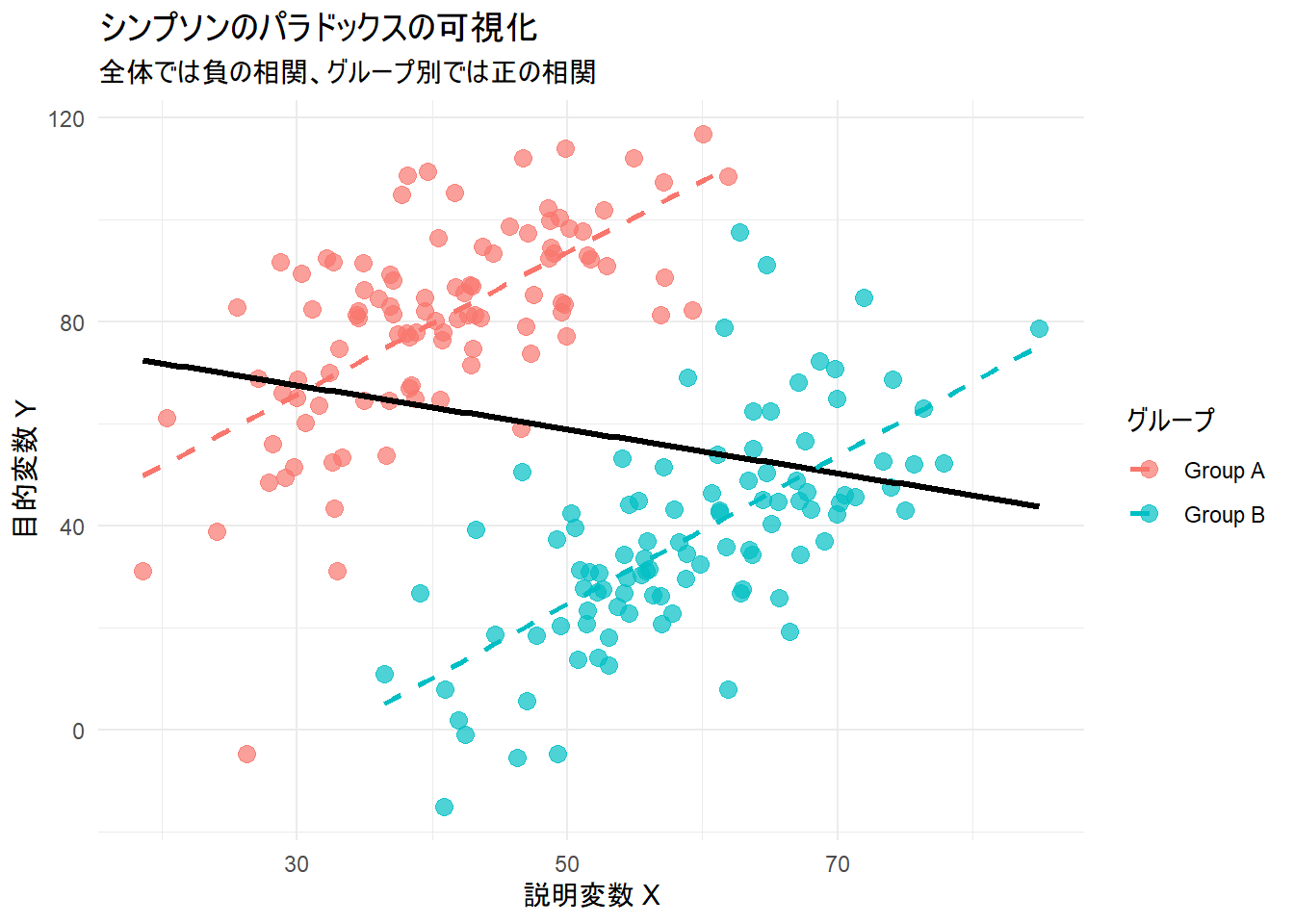Rで シンプソンのパラドックス を試みます。
1. シンプソンのパラドックスとは
シンプソンのパラドックスとは、「複数のグループに分けてデータを分析した結果と、それらをまとめて(集計して)分析した結果が、正反対になる」という統計学上の現象です。
この逆転現象は、データに影響を与える「潜在変数(Lurking Variable)」や「交絡変数(Confounding Variable)」と呼ばれる、隠れた要因を見落とすことで発生します。全体で見たときの相関関係が、実際にはこれらの潜在変数によって作り出された「見せかけの相関」である可能性があります。
具体例:2つの治療法の効果測定
ある病気に対する2つの治療法(治療A、治療B)の効果を比較する例を考えてみましょう。
【全体のデータ】
まず、全体のデータを見てみます。100人ずつの患者に各治療を行ったところ、治療Bの方が成功率が高いという結果になりました。
| 治療法 | 成功者数 | 患者総数 | 成功率 |
|---|---|---|---|
| 治療A | 35人 | 100人 | 35% |
| 治療B | 75人 | 100人 | 75% |
この結果だけを見ると、「治療Bの方が圧倒的に優れた治療法だ」と結論付けてしまいそうです。
【データをグループ分けして見る】
しかし、ここで患者の状態に「軽症」と「重症」という違いがあったことが分かりました。この「症状の重さ」という潜在変数でデータをグループ分けして、分析し直してみましょう。
軽症患者のデータ
| 治療法 | 成功者数 | 患者総数 | 成功率 |
|---|---|---|---|
| 治療A | 19人 | 20人 | 95% |
| 治療B | 72人 | 80人 | 90% |
軽症患者のグループでは、治療Aの方が成功率が高いことが分かります。
重症患者のデータ
| 治療法 | 成功者数 | 患者総数 | 成功率 |
|---|---|---|---|
| 治療A | 16人 | 80人 | 20% |
| 治療B | 3人 | 20人 | 15% |
重症患者のグループでも、治療Aの方が成功率が高いという結果になりました。
【結果の逆転】
結果を整理すると、以下のようになります。
- 軽症グループ: 治療A (95%) > 治療B (90%)
- 重症グループ: 治療A (20%) > 治療B (15%)
- 全体の合計: 治療A (35%) < 治療B (75%)
つまり、「軽症」、「重症」のどちらのグループにおいても治療Aの方が効果的なのに、全体を合計すると治療Bの方が効果的に見えてしまうのです。これがシンプソンのパラドックスです。
なぜこの現象が起きたのか?
この例では、治療法の選択に患者の「症状の重さ」という潜在変数が強く影響しています。
- 治療A: 主に重症患者(80人)に適用されていた。
- 治療B: 主に軽症患者(80人)に適用されていた。
重症患者はもともと成功率が低いため、治療Aのグループには成功率が低い患者が大多数を占めることになり、全体の成功率が35%まで押し下げられました。 逆に、治療Bのグループはもともと成功率が高い軽症患者が大多数だったため、全体の成功率が75%まで大きく底上げされたのです。
このように、データを正しく理解するためには、集計された結果だけでなく、データを適切なグループに分けて分析することが非常に重要です。
2. R言語によるシミュレーション
次に、このパラドックスをR言語でシミュレーションしてみましょう。ここでは、散布図上で「全体で見ると負の相関があるように見えるが、グループ別に見ると正の相関がある」というデータセットを人工的に作成し、可視化します。
シミュレーションコード
# パッケージの読み込み
library(ggplot2)
# 再現性のための乱数シードを設定
seed <- 20250729
set.seed(seed)
# --- ステップ1: データの生成 ---
# グループAのデータを生成 (右肩上がりの相関を持つ)
# xは平均40、yはxに比例しつつ平均80あたりに分布
n_A <- 100
x_A <- rnorm(n_A, mean = 40, sd = 10)
y_A <- 1.5 * x_A + rnorm(n_A, mean = 20, sd = 15)
# グループBのデータを生成 (こちらも右肩上がりの相関を持つ)
# xは平均60、yはxに比例しつつ平均40あたりに分布
n_B <- 100
x_B <- rnorm(n_B, mean = 60, sd = 10)
y_B <- 1.5 * x_B + rnorm(n_B, mean = -50, sd = 15)
# データを1つのデータフレームに結合
sim_data <- data.frame(
x = c(x_A, x_B),
y = c(y_A, y_B),
group = factor(c(rep("Group A", n_A), rep("Group B", n_B)))
)
# --- ステップ2: 全体の相関関係の分析(パラドックスの側面)---
# 全体データに対して線形回帰モデルをあてはめる
overall_model <- lm(y ~ x, data = sim_data)
cat("--- 全体データの回帰分析結果 ---\n")
# Coefficientsのxの係数(傾き)に注目
print(summary(overall_model))
# --- ステップ3: グループ別の相関関係の分析(真実の側面)---
# グループAのデータに対して線形回帰モデルをあてはめる
group_A_model <- lm(y ~ x, data = subset(sim_data, group == "Group A"))
cat("\n--- グループAの回帰分析結果 ---\n")
print(summary(group_A_model))
# グループBのデータに対して線形回帰モデルをあてはめる
group_B_model <- lm(y ~ x, data = subset(sim_data, group == "Group B"))
cat("\n--- グループBの回帰分析結果 ---\n")
print(summary(group_B_model))
# --- ステップ4: 可視化による確認 ---
# ggplot2を使ってプロットを作成
p <- ggplot(sim_data, aes(x = x, y = y)) +
# グループごとに色分けした散布図
geom_point(aes(color = group), alpha = 0.7, size = 3) +
# 全体データの回帰直線(黒い実線)
# この線は右肩下がりになる
geom_smooth(method = "lm", se = FALSE, color = "black", formula = y ~ x, size = 1.2) +
# グループごとの回帰直線(グループと同じ色)
# これらの線は右肩上がりになる
geom_smooth(aes(color = group), method = "lm", se = FALSE, formula = y ~ x, linetype = "dashed") +
# グラフのタイトルとラベルを設定
labs(
title = "シンプソンのパラドックスの可視化",
subtitle = "全体では負の相関、グループ別では正の相関",
x = "説明変数 X",
y = "目的変数 Y",
color = "グループ"
) +
theme_minimal()
# グラフを表示
print(p)--- 全体データの回帰分析結果 ---
Call:
lm(formula = y ~ x, data = sim_data)
Residuals:
Min 1Q Median 3Q Max
-78.083 -22.006 -0.157 21.610 62.139
Coefficients:
Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept) 80.5257 7.9374 10.145 < 2e-16 ***
x -0.4314 0.1542 -2.798 0.00565 **
---
Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
Residual standard error: 28.83 on 198 degrees of freedom
Multiple R-squared: 0.03803, Adjusted R-squared: 0.03317
F-statistic: 7.827 on 1 and 198 DF, p-value: 0.005655
--- グループAの回帰分析結果 ---
Call:
lm(formula = y ~ x, data = subset(sim_data, group == "Group A"))
Residuals:
Min 1Q Median 3Q Max
-65.305 -9.977 1.071 8.890 31.555
Coefficients:
Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept) 23.9374 7.0453 3.398 0.000984 ***
x 1.3941 0.1704 8.183 1.03e-12 ***
---
Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
Residual standard error: 15.43 on 98 degrees of freedom
Multiple R-squared: 0.4059, Adjusted R-squared: 0.3998
F-statistic: 66.96 on 1 and 98 DF, p-value: 1.032e-12
--- グループBの回帰分析結果 ---
Call:
lm(formula = y ~ x, data = subset(sim_data, group == "Group B"))
Residuals:
Min 1Q Median 3Q Max
-34.053 -9.756 -2.219 6.511 54.281
Coefficients:
Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept) -47.7772 9.7233 -4.914 3.58e-06 ***
x 1.4493 0.1623 8.930 2.54e-14 ***
---
Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
Residual standard error: 15.48 on 98 degrees of freedom
Multiple R-squared: 0.4486, Adjusted R-squared: 0.443
F-statistic: 79.74 on 1 and 98 DF, p-value: 2.541e-14コードの解説と結果の解釈
- データの生成:
-
Group AとGroup Bという2つのデータ群を生成します。 - どちらのグループも、
yは1.5 * xという関係を基本としているため、本来は強い正の相関(右肩上がり)を持っています。 - ただし、
Group Aは(x, y)が(40, 80)あたりに、Group Bは(60, 40)あたりに分布するように平均値を調整しています。groupが潜在変数です。
-
- 全体の分析:
-
lm(y ~ x, data = sim_data)で全体データに対する回帰直線の傾きを計算します。 - 出力される
Coefficients:のxの行を見ると、Estimate(係数)が負の値(-0.4314)になっています。これは「xが増えるとyが減る」という負の相関を示唆しています。
-
- グループ別の分析:
-
subset()でデータをグループに分け、それぞれの回帰直線の傾きを計算します。 -
Group A、Group Bどちらのモデルでも、xの係数が正の値(1.5に近い値)になっています。これは「xが増えるとyが増える」という正の相関を示しており、こちらがデータの真の姿です。
-
- 可視化:
- 生成されたグラフを見ると、一目瞭然です。
- 黒い実線(全体)は、右肩下がりの負の相関を示しています。
- しかし、色分けされた点(グループ)は2つの塊に分かれており、それぞれの塊の中では破線(グループごと)が示すように、明確な右肩上がりの正の相関が見られます。
このシミュレーションは、潜在変数であるgroupを無視してデータを集計してしまうと、個々のグループが持つ本来の傾向(正の相関)とは正反対の結論(負の相関)を導き出してしまう危険性を示しています。
以上です。