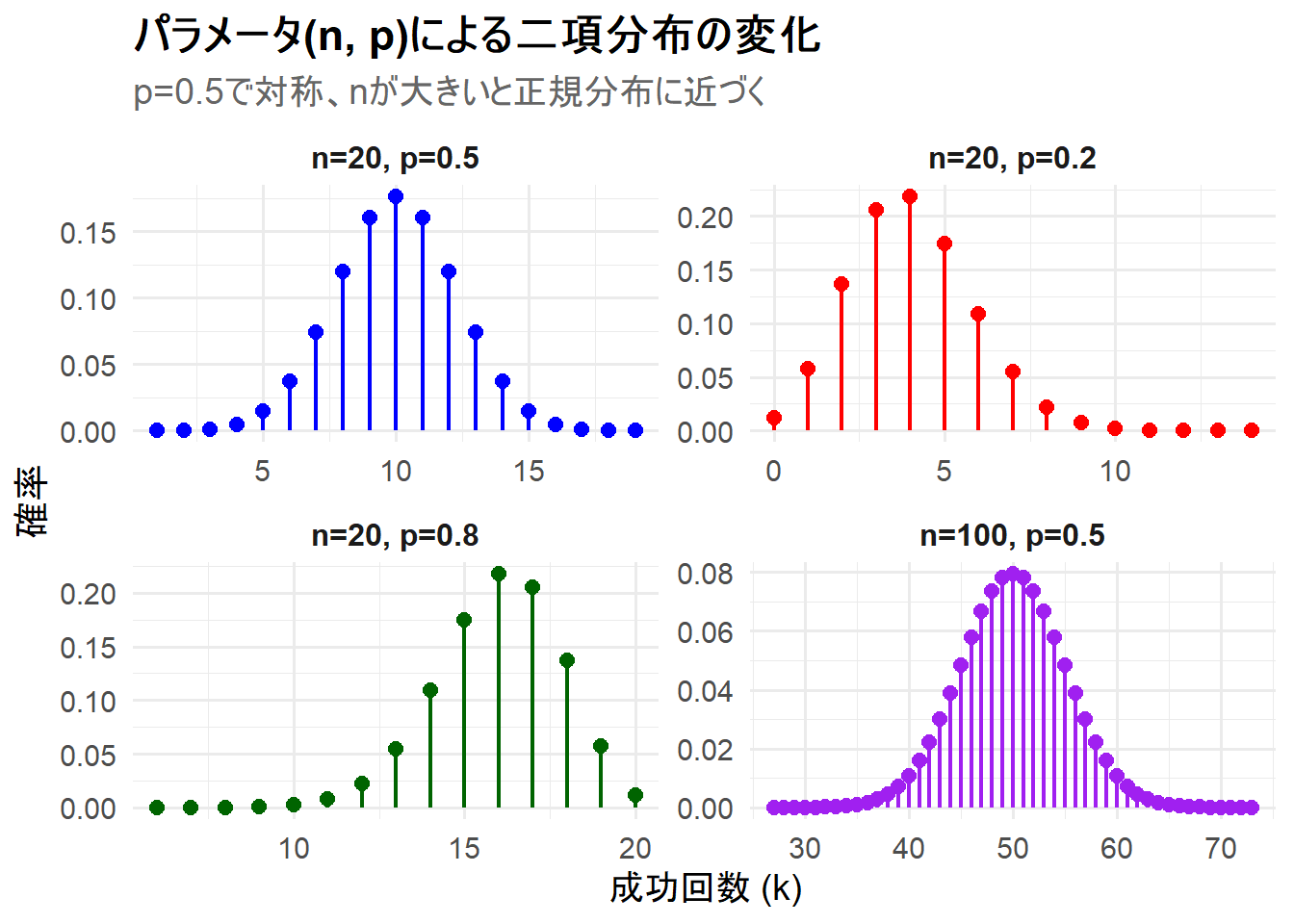Rで 確率分布:二項分布 を試みます。
本ポストはこちらの続きです。

Rで確率分布:ポアソン分布
const typesetMath = (el) => { if (window.MathJax) { // MathJax Typeset window.MathJax.typeset(); } else if (window.katex...
1. 二項分布とは
二項分布(Binomial Distribution)は、離散確率分布の一つです。これは、「成功か失敗か」、「表か裏か」といった、結果が2種類しかない試行(ベルヌーイ試行)を、独立にn回繰り返したときに、成功する回数が従う分布です。
例えば、「コインを10回投げて、表が出る回数」や「100個の製品を検査して、不良品が見つかる個数」などが、二項分布に従う典型的な例です。
確率質量関数 (Probability Mass Function, PMF)
試行回数 \(n\)、成功確率 \(p\) の二項分布に従う確率変数 \(X\) が、特定の値 \(k\)(成功回数)をとる確率 \(P(X=k)\) は、以下の式で定義されます。
\[P\left(X=k | n, p\right) = \binom{n}{k} p^k \left(1-p\right)^{n-k} \quad (k=0, 1, 2, \dots, n)\]
この式は、以下の3つの要素から成り立っています。
- \(\binom{n}{k} = \dfrac{n!}{k!(n-k)!}\): 組み合わせの数。\(n\)回の試行の中から、成功する\(k\)回をどの順番で選ぶかのパターン数です。
- \(p^k\): 成功がk回起こる確率。
- \((1-p)^{n-k}\): 失敗がn-k回起こる確率。
この分布は、2つのパラメータによってその形状が決定されます。
- \(n\): 試行回数 (number of trials)
- 独立なベルヌーイ試行を繰り返す回数です。正の整数です。
- \(p\): 成功確率 (probability of success)
- 1回の試行で「成功」と見なす結果が起こる確率です。\(0 \le p \le 1\) の範囲の値をとります。
主な特徴
- 定義域: 成功回数 \(k\) がとりうる値は、0から試行回数nまでの整数です。
- 形状:
- \(p=0.5\) のとき、分布は左右対称な釣鐘型になります。
- \(p < 0.5\) のとき、分布は右に歪んだ形状になります。
- \(p > 0.5\) のとき、分布は左に歪んだ形状になります。
- 試行回数 \(n\) が大きくなるにつれて、分布の形状は(\(p\)が0や1に極端に近くない限り)正規分布で近似できるようになります(ド・モアブル–ラプラスの定理)。
- 代表値:
- 平均 (Mean): \(E[X] = np\)
- 分散 (Variance): \(V[X] = np(1-p)\)
- 他の分布との関係:
- ベルヌーイ分布: 試行回数 \(n=1\) の二項分布は、ベルヌーイ分布と一致します。
- ポアソン分布: \(n\) が非常に大きく、\(p\) が非常に小さい場合、\(\lambda = np\) のポアソン分布で近似できます。
2. 二項分布の応用例
結果が2値で表される試行の繰り返しは、現実世界に数多く存在します。
- 品質管理
- 工場で生産された製品を \(n\) 個抜き取って検査したときの、不良品の個数。
- A/Bテスト・マーケティング
- \(n\) 人のユーザーに新しいWebサイトのデザインを見せたときの、コンバージョン(購入や登録)した人数。
- \(n\) 人にダイレクトメールを送ったときの、返信があった人数。
- 医療・薬学
- \(n\) 人の患者に新薬を投与したときの、副作用が出た(あるいは、効果があった)患者の数。
- 世論調査
- \(n\) 人の有権者に質問したときの、ある政策への賛成者の数。
- 遺伝学
- ある遺伝子を持つ両親から生まれる \(n\) 人の子供のうち、特定の遺伝形質を受け継ぐ子供の数。
3. R言語によるシミュレーション
ここでは、試行回数 \(n\) と成功確率 \(p\) を変更した4つの二項分布を1枚のチャートに描画します。ポアソン分布と同様にロリポップチャートで表現します。
- ケース1:
n=20, p=0.5(対称な釣鐘型) - ケース2:
n=20, p=0.2(右に歪んだ形状) - ケース3:
n=20, p=0.8(左に歪んだ形状) - ケース4:
n=100, p=0.5(試行回数が大きく、正規分布に近い形状)
Rコード
# 必要なライブラリを読み込みます
library(ggplot2)
library(dplyr)
library(tidyr)
# 1. 異なるパラメータを持つ二項分布の確率質量を計算
# dbinom(k, size, prob) を使用。sizeがn, probがp
df <- tibble(
k = 0:100
) %>%
mutate(
`n=20, p=0.5` = dbinom(k, size = 20, prob = 0.5),
`n=20, p=0.2` = dbinom(k, size = 20, prob = 0.2),
`n=20, p=0.8` = dbinom(k, size = 20, prob = 0.8),
`n=100, p=0.5` = dbinom(k, size = 100, prob = 0.5)
)
# 2. ggplotで描画しやすいように、データを「ロングフォーマット」に変換
df_long <- df %>%
pivot_longer(
cols = -k,
names_to = "parameters",
values_to = "probability"
) %>%
# 確率が非常に小さいものは除外してプロットを見やすくする
filter(probability > 1e-6) %>%
# 凡例の順序を調整
mutate(parameters = factor(parameters, levels = c(
"n=20, p=0.5",
"n=20, p=0.2",
"n=20, p=0.8",
"n=100, p=0.5"
)))
# 3. 各分布に割り当てる色を定義
manual_colors <- c(
`n=20, p=0.5` = "blue",
`n=20, p=0.2` = "red",
`n=20, p=0.8` = "darkgreen",
`n=100, p=0.5` = "purple"
)
# 4. ggplotを使用してチャートを描画(ファセットで分割)
p <- ggplot(df_long, aes(x = k, y = probability, color = parameters)) +
geom_segment(aes(xend = k, yend = 0), linewidth = 0.8) +
geom_point(size = 2.5) +
facet_wrap(~parameters, ncol = 2, scales = "free") +
scale_color_manual(values = manual_colors) +
labs(
title = "パラメータ(n, p)による二項分布の変化",
subtitle = "p=0.5で対称、nが大きいと正規分布に近づく",
x = "成功回数 (k)",
y = "確率"
) +
theme_minimal(base_size = 14) +
theme(
legend.position = "none",
plot.title = element_text(face = "bold"),
plot.subtitle = element_text(color = "gray40"),
strip.text = element_text(face = "bold", size = 12)
)
# チャートの表示
print(p)Figure 1 の解説
上記のRコードを実行すると、4つの二項分布が描画されたチャート Figure 1 が生成されます。
-
n=20, p=0.5(左上): 成功確率が0.5なので、分布は平均 \(np=10\) を中心とした左右対称な釣鐘型になっています。 -
n=20, p=0.2(右上): 成功確率が0.5より小さいため、分布は左に寄っており(平均は \(np=4\))、右に歪んだ形状をしています。成功回数が少ない方に確率が偏っています。 -
n=20, p=0.8(左下): 成功確率が0.5より大きいため、分布は右に寄っており(平均は \(np=16\))、左に歪んだ形状をしています。成功回数が多い方に確率が偏っています。 -
n=100, p=0.5(右下): 試行回数 \(n\) が100と大きくなっています。\(p=0.5\) のため対称なのはもちろんですが、個々の点の離散的な性質が目立たなくなり、全体として滑らかな、正規分布に似た釣鐘型になっていることがわかります。
以上です。