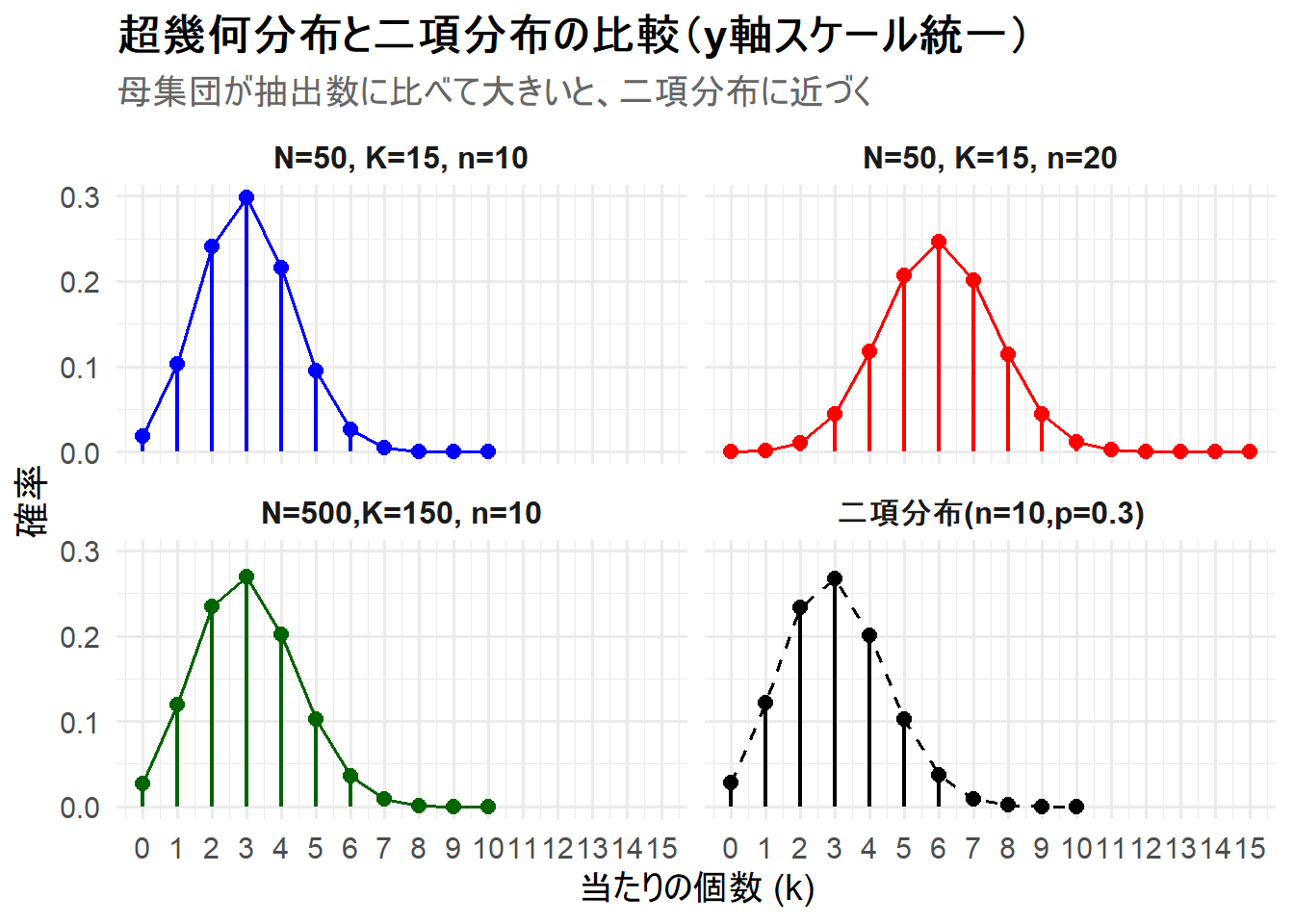Rで 確率分布:超幾何分布 を試みます。
本ポストはこちらの続きです。

Rで確率分布:幾何分布
const typesetMath = (el) => { if (window.MathJax) { // MathJax Typeset window.MathJax.typeset(); } else if (window.katex...
1. 超幾何分布とは
超幾何分布(Hypergeometric Distribution)は、「当たり」と「ハズレ」の2種類のものが入った母集団から、非復元抽出(一度引いたものは元に戻さない)で標本をいくつか引いたときに、その標本に含まれる「当たりの個数」が従う離散確率分布です。
二項分布が「復元抽出」(くじを引くたびに元に戻すため、当たりを引く確率は常に一定)の状況をモデル化するのに対し、超幾何分布は「非復元抽出」(くじを引くたびに当たりが減ったり、全体の数が減ったりするため、当たりを引く確率が変動する)の状況をモデル化する点が本質的な違いです。
確率質量関数 (PMF)
\(N\)個の要素からなる母集団に、\(K\)個の「当たり」が含まれているとします。この母集団から\(n\)個の標本を非復元抽出したとき、その中に\(k\)個の当たりが含まれる確率 \(P(X=k)\) は、以下の式で定義されます。
\[P\left(X=k | N, K, n\right) = \dfrac{\binom{K}{k} \binom{N-K}{n-k}}{\binom{N}{n}}\]
この式は、組み合わせの数の比で構成されています。
- 分母 \(\binom{N}{n}\): 全\(N\)個から\(n\)個を選ぶ、すべての可能な組み合わせの総数。
- 分子 \(\binom{K}{k} \binom{N-K}{n-k}\):
- \(\binom{K}{k}\): 全\(K\)個の当たりから\(k\)個を選ぶ組み合わせの数。
- \(\binom{N-K}{n-k}\): 全\(N-K\)個のハズレから、残りの\(n-k\)個を選ぶ組み合わせの数。
- これらの積が、条件を満たす組み合わせの数となります。
この分布は、3つのパラメータによってその形状が決定されます。
- \(N\): 母集団の総数 (population size)
- \(K\): 母集団に含まれる当たりの総数 (number of successes in population)
- \(n\): 抽出する標本のサイズ (sample size)
主な特徴
- 定義域: 当たりの個数 \(k\) がとりうる値は、\(\max(0, n-(N-K)) \le k \le \min(n, K)\) の範囲の整数です。
- 形状: 二項分布と同様に、釣鐘型の分布になりますが、非復元抽出の影響で、二項分布よりも分散が小さく(ピークが鋭く)なる傾向があります。
- 代表値:
- 平均 (Mean): \(E[X] = n \dfrac{K}{N}\)
- 分散 (Variance): \(V[X] = n \dfrac{K}{N} \left(1-\dfrac{K}{N}\right) \dfrac{N-n}{N-1}\)
- 分散の式に現れる \(\dfrac{N-n}{N-1}\) は有限母集団修正(finite population correction)と呼ばれ、非復元抽出による分散の減少を表します。母集団の総数 \(N\) が標本サイズ \(n\) に比べて非常に大きい場合、この項は1に近づき、超幾何分布は二項分布で近似できます。
2. 超幾何分布の応用例
非復元抽出が本質となる場面で応用されます。
- 品質管理
- \(N\)個の製品ロットの中に\(K\)個の不良品が含まれていると仮定し、\(n\)個を抜き取り検査したときの、不良品の個数の確率分布。これにより、ロット全体の品質を推測し、合格・不合格を判定します。
- 遺伝学
- 特定の遺伝子を持つ個体が\(K\)匹いる、閉鎖された\(N\)匹の個体群から、\(n\)匹を捕獲したときの、その遺伝子を持つ個体の数。
- カードゲーム
- 52枚のトランプの山札(\(N=52\))から、最初に配られた5枚の手札(\(n=5\))の中に、エース(\(K=4\))が何枚含まれているか、といった確率の計算。
- フィッシャーの正確確率検定
- 2×2の分割表における周辺度数を固定した条件下で、セルの度数が観測された値以上(あるいは以下)に偏る確率を計算するために、超幾何分布が直接利用されます。これは、サンプルサイズが小さい場合の独立性の検定で利用されます。
3. R言語によるシミュレーション
ここでは、パラメータを変更した3つの超幾何分布と、比較対象として対応する二項分布を1枚のチャートに描画します。これにより、非復元抽出の影響(有限母集団修正の効果)を視覚的に理解します。
- ケース1:
N=50, K=15, n=10(標準的なケース) - ケース2:
N=50, K=15, n=20(抽出数を増やす) - ケース3:
N=500, K=150, n=10(母集団を大きくする → 二項分布に近づく) - 比較対象: 二項分布
n=10, p=15/50(ケース1に対応する復元抽出の場合)
Rコード
# 必要なライブラリを読み込みます
library(ggplot2)
library(dplyr)
library(tidyr)
# 1. 描画範囲となるx軸の値(当たりの個数)を生成
k_vals <- 0:20
# 2. 異なるパラメータを持つ超幾何分布と二項分布の確率質量を計算
# dhyper(x, m, n, k) -> x:当たりの個数, m:母集団の当たり数, n:母集団のハズレ数, k:抽出数
df <- tibble(
k = k_vals
) %>%
mutate(
`N=50, K=15, n=10` = dhyper(k, m = 15, n = 50 - 15, k = 10),
`N=50, K=15, n=20` = dhyper(k, m = 15, n = 50 - 15, k = 20),
`N=500,K=150, n=10` = dhyper(k, m = 150, n = 500 - 150, k = 10),
`二項分布(n=10,p=0.3)` = dbinom(k, size = 10, prob = 15 / 50)
)
# 3. ggplotで描画しやすいように、データを「ロングフォーマット」に変換
df_long <- df %>%
pivot_longer(
cols = -k,
names_to = "parameters",
values_to = "probability"
) %>%
filter(probability > 1e-9) %>%
mutate(parameters = factor(parameters, levels = c(
"N=50, K=15, n=10",
"N=50, K=15, n=20",
"N=500,K=150, n=10",
"二項分布(n=10,p=0.3)"
)))
# 4. 各分布に割り当てる色と線種を定義
manual_colors <- c(
`N=50, K=15, n=10` = "blue",
`N=50, K=15, n=20` = "red",
`N=500,K=150, n=10` = "darkgreen",
`二項分布(n=10,p=0.3)` = "black"
)
manual_linetypes <- c(
`N=50, K=15, n=10` = "solid",
`N=50, K=15, n=20` = "solid",
`N=500,K=150, n=10` = "solid",
`二項分布(n=10,p=0.3)` = "dashed"
)
# 5. ggplotのコード
p <- ggplot(df_long, aes(x = k, y = probability, color = parameters)) +
geom_segment(aes(xend = k, yend = 0), linewidth = 0.8) +
geom_point(size = 2.5) +
geom_line(aes(linetype = parameters), linewidth = 0.7) +
facet_wrap(~parameters, ncol = 2, scales = "fixed") +
# x軸の目盛りを整数にする
scale_x_continuous(breaks = function(x) floor(min(x)):ceiling(max(x))) +
# xlim(c(0,10)) +
scale_color_manual(values = manual_colors) +
scale_linetype_manual(values = manual_linetypes, guide = "none") +
guides(color = guide_legend(override.aes = list(linetype = "solid"))) +
labs(
title = "超幾何分布と二項分布の比較(y軸スケール統一)",
subtitle = "母集団が抽出数に比べて大きいと、二項分布に近づく",
x = "当たりの個数 (k)",
y = "確率"
) +
theme_minimal(base_size = 14) +
theme(
legend.position = "none",
plot.title = element_text(face = "bold"),
plot.subtitle = element_text(color = "gray40"),
strip.text = element_text(face = "bold", size = 12)
)
# チャートの表示
print(p)Figure 1 の解説
上記のRコードを実行すると、3つの超幾何分布と1つの二項分布が描画されたチャート Figure 1 が生成されます。
-
N=50, K=15, n=10(左上) と二項分布(n=10,p=0.3)(右下) の比較:- ピークの高さ: 超幾何分布(左上)のピーク(\(k=3\)で約0.3)は、二項分布(右下)のピーク(\(k=3\)で約0.267)よりも高くなっています。
- 裾の短さ: \(k=0\) および \(k=7\) の場合の二項分布と比較した確率は以下の通り、超幾何分布の方が二項分布より低くなっています。これは、超幾何分布が二項分布よりも平均の周りに確率が集中しており、裾が短い(ばらつきが小さい)ことを示しています。
# 1. 超幾何分布の確率を計算
prob_hyper_k0 <- dhyper(
x = 0, # 標本中の当たりの数 (k)
m = 15, # 母集団の当たりの総数 (K)
n = 50 - 15, # 母集団のハズレの総数 (N-K)
k = 10
) # 抽出する標本のサイズ (n)
prob_hyper_k7 <- dhyper(
x = 7,
m = 15,
n = 50 - 15,
k = 10
)
prob_hyper_k3 <- dhyper(
x = 3,
m = 15,
n = 50 - 15,
k = 10
)
# 2. 二項分布の確率を計算
prob_binom_k0 <- dbinom(
x = 0, # 成功回数 (k)
size = 10, # 試行回数 (n)
prob = 0.3
) # 成功確率 (p)
prob_binom_k7 <- dbinom(
x = 7,
size = 10,
prob = 0.3
)
prob_binom_k3 <- dbinom(
x = 3,
size = 10,
prob = 0.3
)
# 3. 結果を表示
print(paste("超幾何分布 (N=50, K=15, n=10) で k=0 となる確率:", prob_hyper_k0))
print(paste("二項分布 (n=10, p=0.3) で k=0 となる確率:", prob_binom_k0))
cat("\n")
print(paste("超幾何分布 (N=50, K=15, n=10) で k=7 となる確率:", prob_hyper_k7))
print(paste("二項分布 (n=10, p=0.3) で k=7 となる確率:", prob_binom_k7))
cat("\n")
print(paste("超幾何分布 (N=50, K=15, n=10) で k=3 となる確率:", prob_hyper_k3))
print(paste("二項分布 (n=10, p=0.3) で k=3 となる確率:", prob_binom_k3))[1] "超幾何分布 (N=50, K=15, n=10) で k=0 となる確率: 0.017871341971262"
[1] "二項分布 (n=10, p=0.3) で k=0 となる確率: 0.0282475249"
[1] "超幾何分布 (N=50, K=15, n=10) で k=7 となる確率: 0.00410007150341801"
[1] "二項分布 (n=10, p=0.3) で k=7 となる確率: 0.00900169199999999"
[1] "超幾何分布 (N=50, K=15, n=10) で k=3 となる確率: 0.297855699521034"
[1] "二項分布 (n=10, p=0.3) で k=3 となる確率: 0.266827932"-
N=500,K=150, n=10(左下) と二項分布(n=10,p=0.3)(右下) の比較:- この2つのグラフは、視覚的にほとんど区別がつきません。ピークの高さも、裾の広がりもほぼ同じです。
- これは、母集団のサイズ(\(N=500\))が抽出数(\(n=10\))に比べて非常に大きいため、非復元抽出の影響(有限母集団修正項 \(\frac{N-n}{N-1}\) がほぼ1になる)が無視できるほど小さくなり、超幾何分布が二項分布に収束していることを示しています。
-
N=50, K=15, n=20(右上):- 抽出数\(n\)が20と大きいため、分布の横幅が広がり、その分ピークの高さは他のケースより低くなっていることがわかります。
以上です。